STM32入門(組み込み開発)
■第11話:STM32のまとめと応用(自動サンプラー)
(最終更新日:2025.03.01)

(絵が小さい場合はスマホを横に)
「応用、これからの組み込み機器」
本記事では、STM32を用いた自動サンプラーの開発事例を紹介する。
自動サンプラーは、試料の吸引・分注を正確に行い、測定器へ送る装置である。
本プロジェクトでは、ステッピングモーターによる精密制御、PID制御による流量調整、UARTやRS-485による通信制御など、
組み込みシステムの重要な要素を活用した。
さらに、エラー処理やデータロギングを実装し、安定した動作を確保した。
本記事では、システムの設計から実装、応用分野までを詳しく解説し、組み込み開発の実践的な知識を提供する。
[目次]
1.応用例:自動サンプラーの作成
1.1 機能要件の設計
自動サンプラーは、特定の液体サンプルを正確に吸引・分注し、測定機器へ送るための装置である。 試料の吸引や分注を自動化し、試料ラックの管理、外部システムとの連携、エラー処理などを考慮した設計が必要になる。 サンプラーの基本機能として、まず試料の吸引・分注を行い、指定された量の液体を正確に制御する必要がある。 また、複数の試料を管理するためのラック制御が必要であり、これにより試料の移動や試験の自動化を実現する。 さらに、ホストPCやPLCなどの外部システムからの指示を受け、動作を開始する仕組みも重要だ。

サンプル瓶から自動で吸引、注入する
CPUボードは特に種類は問わないが、実例が豊富なSTM32をマイコンとして採用する。 リアルタイム性が求められるため、割り込み機能を活用し、低消費電力モードを用いることで省エネ運用することも大事だ。 また、ステッピングモーターを利用してX-Y-Z軸の移動を精密に制御し、試料の吸引ポイントを正確に決定することが大事だ。 サンプラーのポンプ動作にはPID制御を導入し、流量を適切に調整することで安定した吸引・排出を可能にする。 さらに、7セグメントディスプレイを搭載し、試料の状態やシステムのステータスをリアルタイムで表示できるようにすることが必要だ。

ディスプレイで状態を表示
通信仕様については、ホストPCやPLCとのデータのやり取りにUART通信を使用し、ノイズ耐性を考慮してRS-485も採用した。 また、液面センサーや温度センサーとの通信にはI2Cバスを活用し、シンプルな配線で効率的なデータ取得を実現した。 安全設計も重要なポイントであり、モーターの過熱を防ぐための温度監視機能を実装し、非常停止スイッチを備えることで異常時の動作停止を可能にした。 さらに、動作ログをSDカードに記録することで、トラブルシューティングの際に詳細な情報を参照できるようになる。
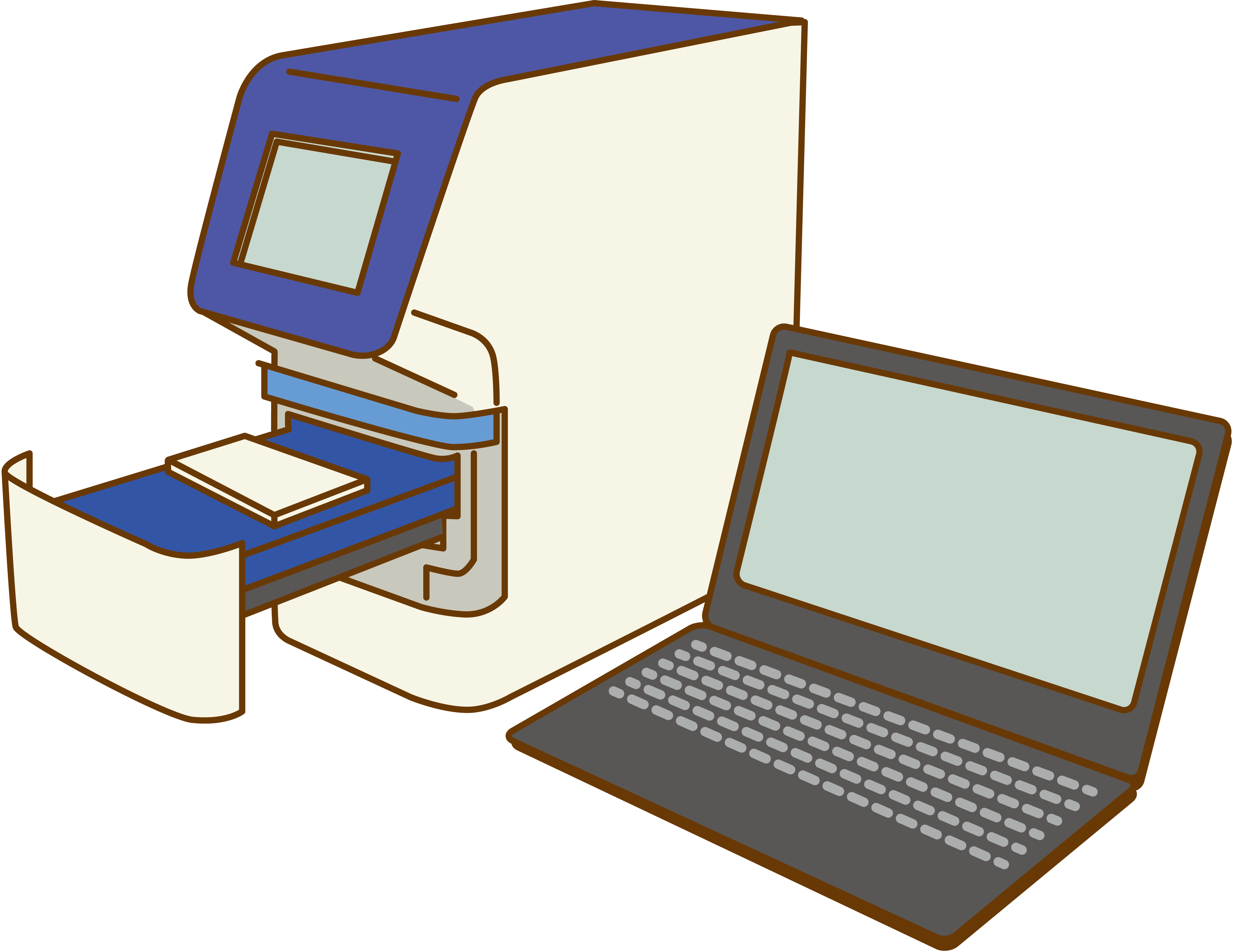
ホストPCからの制御
1.2 組み込みシステム全体の流れ
システムの動作フローは、大きく分けて初期化、スタンバイモード、試料の吸引、分注、ログ記録、エラー処理の6つのステップで構成される。
まず、電源投入後、各センサー、モーター、ディスプレイの動作確認を行い、フラッシュメモリやEEPROMから前回の動作履歴を読み込む。
次に、スタンバイモードに入り、ホストPCやPLCからのコマンドを待機する。
ディスプレイには「READY」の表示を行い、オペレーターがシステムの準備完了を確認できるようにする。
試料の吸引プロセスでは、液面センサーを利用して試料の存在を確認し、ステッピングモーターを駆動して吸引位置へ移動する。
ポンプをPID制御しながら吸引し、流量センサーで試料量の誤差をチェックする。
吸引が完了した後、目的の容器位置へ移動し、分注量を制御しながら試料を排出する。
分注後は、空気パージを行い、チューブ内の残留液を除去することで次の試料との混ざりを防ぐ。
システムの動作ログは、SDカードに記録され、吸引量、試料識別番号、エラーステータスなどの情報が保存される。
これにより、トラブル発生時に詳細な履歴を確認することができる。
また、エラーが発生した際には、液面検知エラーやモーター異常などを検知し、動作を即座に停止する。
エラーコードはディスプレイに表示され、ログにも記録されるため、後のデバッグが容易になる。
2.総括と次のステップ
2.1 STM32の学びを振り返る
今回のプロジェクトでは、STM32を活用したリアルタイム制御や通信制御、PID制御の実装について多くの学びがあった。 特に、割り込み処理の設計では、各タスクの優先度を適切に設定し、リアルタイム性を確保することが重要である。 また、UART通信では、ノイズ耐性を考慮し、確実にコマンドを受信できるようなエラーハンドリングを実装する。 モーター制御では、ステッピングモーターの加速・減速をスムーズに行い、試料移動時の精度を向上させる。 さらに、データロギングにより、システムの状態を詳細に記録し、トラブル発生時の解析が容易になる。
2.2 応用分野の紹介(AI、IoT、産業機器)
STM32を活用した組み込み開発は、さまざまな分野への応用が可能である。 AIとの融合では、機械学習を用いた異常検知が挙げられる。 例えば、サンプラーの吸引動作に異常がある場合、AIが自動的に判定し、メンテナンスのタイミングを予測できる。 また、画像認識を組み合わせることで、試料の色変化をカメラで監視し、異常を検出することも可能である。 IoT化の観点からは、クラウドと接続して試料情報を収集し、遠隔監視を実現できる。 例えば、MQTTプロトコルを使用してデータを送信し、スマートフォンアプリで装置の状態をリアルタイムに監視することができる。 産業機器への応用では、自動検査装置としての利用が考えられる。 製造ラインにおいて品質管理のために試料を自動的に分析する装置として活用できるほか、医療分野では自動血液分析装置のような応用も考えらえる。
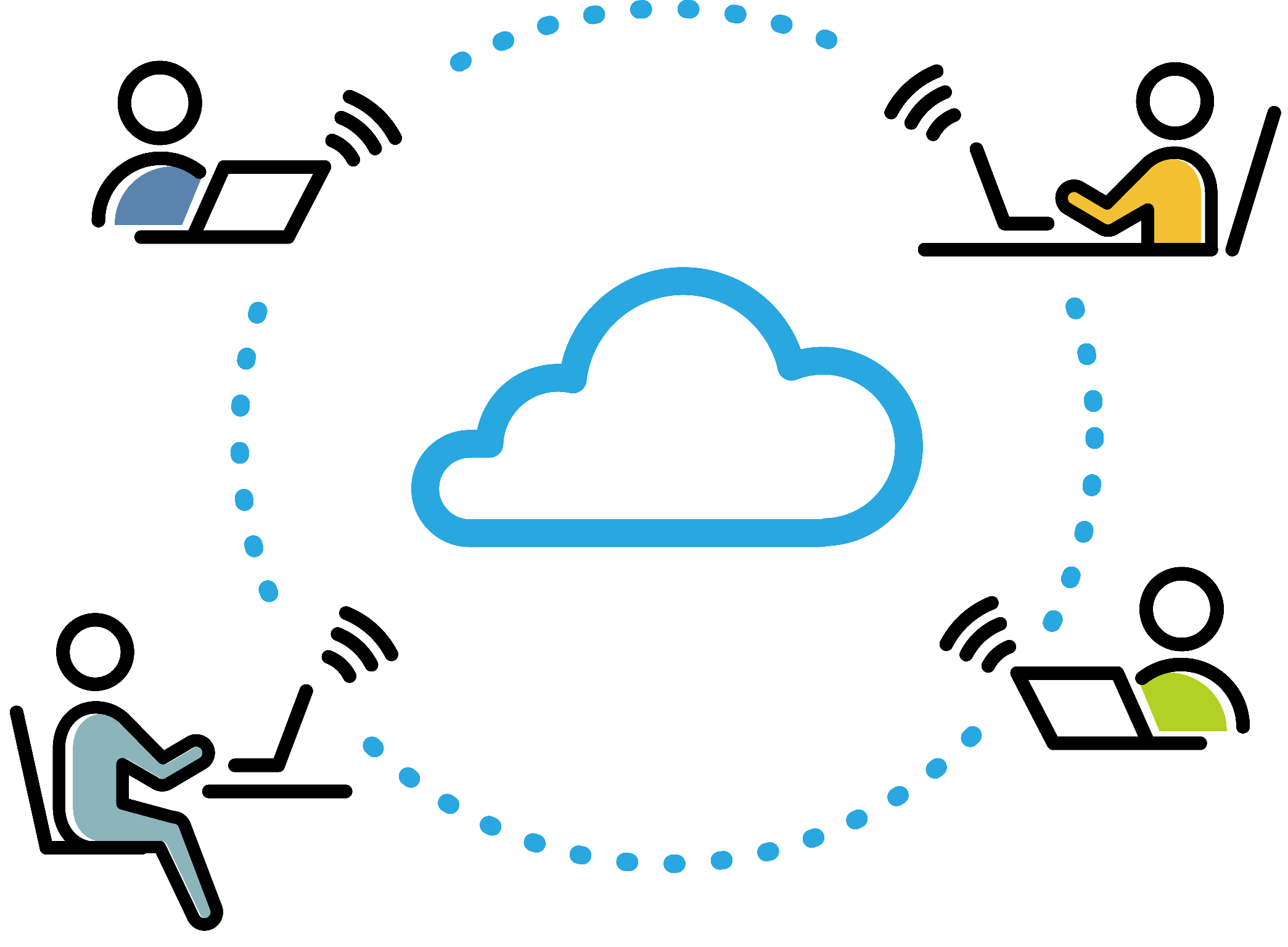
クラウドやAIの活用
3.まとめ
今回は、STM32を活用してリアルタイム制御、通信制御、モーター制御を統合し、試料の吸引・分注を自動化するシステムを紹介した。 割り込み処理を適切に設計し、ステッピングモーターの加速・減速制御を工夫することで、高精度な試料移動を実現する。 また、UART通信を安定化させ、エラーハンドリングを強化することで、産業用途にも適した堅牢なシステムを構築できるようになる。 さらに、データロギングをSDカードに記録し、異常発生時の解析を容易にする。 今後は、AIによる異常検知やクラウドとの連携を視野に入れ、さらなる発展を目指す。 STM32を活用した組み込みシステムの開発は、産業機器や医療機器など、さまざまな分野で応用可能であり、今後の技術進化にも大きく貢献するだろう。
▼参考図書、サイト
STM32マイコン公式日本語サイト
STマイクロエレクトロニクス
「WindowsではじめるSTM32」 インプレスR&D 山本 小鉄